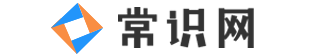日语文学作品赏析:《藤棚》
あちこちに廃墟が出来てから、東京という都会の眺望は随分かわった。小石川の白山から、坂の上にたって、鶏声ケ窪の谷間をみわたすと、段々と低くなってゆく地勢とそこに高低をもって梢を見せている緑の樹木の工合がどこかセザンヌの風景めいた印象をあたえる。巣鴨から来た電車がゆっくり白山を下りて指ケ谷へ出る、その辺で左手の裸の崖を眺めると、くすんだ赤い煉瓦の塀のくずれたところがあったりして、やはり荒廃のうちに一種の美しさが感じられる。この左手の崖の上に、白く大きくコンクリートの建物がのこっているのが遠くからでもよく見えた。そして、そこが西片町の誠之だときくと、わたしは、何だかおどろいて、光る白い建物を眺めやる。大変よく知っている懐しいところの感じと、まるで見知らないよそよそしさの交りあった面白い心持で。――
わたしたち姉弟が、紺絣の筒袖に小倉の小さい袴をはいた男の児と、リボンをお下げの前髪に結んでメリンスの元禄袖の被布をきた少女で、誠之に通っていたころ、学校はどこもかしこも木造で、毎日数百の子供たちの麻裏草履でかけまわられる廊下も階段も、木目がけばだって埃っぽかった。東片町の通りから入って来ると正面が正門で、入ったところから砂利がしきつめられていた。桜の大木が右手に植っていて、その枝の下に、男児の下駄箱、つまり出入口があった。小使室が続いていて、お弁当の時黒いはっぴを着た小使が両手に三つずつ銅のヤカンをもって来て、教壇の上に並べて置いた。そのお湯は、桜の樹の下の小使室の土間を入った右手にある大釜から大きなひしゃくでくみかえされるのであった。
正面に表玄関があって、式のある日はその表玄関が左右にひらかれ、紫メリンスの幕がはられた。そういう日には、黒い学校の門の左右の柱に、必ず大きい日の丸の旗が飾られるのであった。
表玄関を子供たちが出入りするということはなかった。女の児の入口は、左手の、受付と書いてはあるがいつも閉っている小さいガラス戸の横についていて、そこは先生の入口と直角になっていた。先生の入口から入ったところに、長い幅ひろい机をおいた裁縫室があって、窓の下にオルガンがあり、壁に音階表がかけもののように下っていた。裁縫室は音楽室にもなるのであった。田代先生といういつもシングル・カラーをして薄い髭を生やした音楽の先生が、唱歌を教えた。その先生は、冬の寒いとき、子供たちがつい八つくちから手を入れて懐手をしているのをみつけると、そらまた、へそを押えてる! と注意した。上級の女の児は、そう云われることを大変きらった。田代先生は髭のついている口を大きくあけて、男のどら声のような声で、しかし音程は正しく「空も港も夜は更けて」というような単純な歌を教えた。
その室のとなりに教員室があり、子供たちにとって、教員室というところは、なみなみの思いでは入って行けない別世界であった。一人でさえ威風堂々たる先生たちが、二列に並んだ塗テーブルに向いあってぞっくりとかけて居られ、その正面には別に横長テーブルがはなれて置かれていた。そこのテーブルは校長先生の席であった。子供たちは校長先生の白く長く垂れている髯と、うすいあばたの顔を思い出すと黒いフロックコートしか思い浮ばなかった。校長先生はそれほど特別の偉さであった。式は、女の児の三年から六年までの教室をぶっこぬきにしたところで行われた。わたしたちは、そういう式場で「螢の光、まどの雪」という歌をうたい、涙を眼に湛えて誠之を卒業したのであった。
コの字に建てめぐらされた木造二階建の真下が女の遊び場で、左手にずっとひろがった広い砂利敷のところが男児運動場であった。そっちに年を経た藤棚があって、季節になると紫の花房を垂れた。その下はうすぐらくて、いい匂いがした。蜂がたくさん花房のまわりをとんだ。
からりとした男児運動場のところへ、ベビー・オルガンをもち出して、六年女児は体操の時間にカドリールとコチロンを習った。タータタタと空に響くオルガンのメロディーにつれて、えび茶や紫紺の袴をつけた六十人ほどの少女が、向い会って、いっせいにヨーロッパ風に膝をかがめ、舞踏の挨拶をするのであった。その運動場は、トタン塀にかこまれていて、黒板塀の方に桜の樹が並んでいた。その樹の下の地面には毛虫の落す黒い丸い粒があった。教員室と裁縫室の窓はこの運動場に面していて、当番のとき水のみ場のわきにある小さい池の掃除を、いいこころもちで高い声で唱歌をうたいながらしていると、先生の顔が上の窓から覗くことがあった。覗かれると、どうかしてもう歌はとまってしまうのだった。

扫扫上方二维码领取资料

点击排行
- 2 上升
- 3 上升
- 4 上升
- 5 上升
- 6 上升
- 7 上升
- 8 上升
- 9 上升
- 10 上升